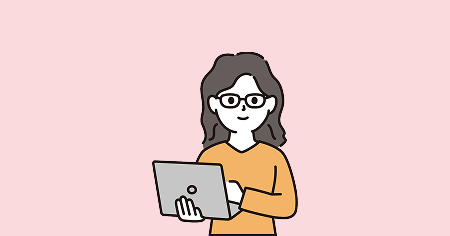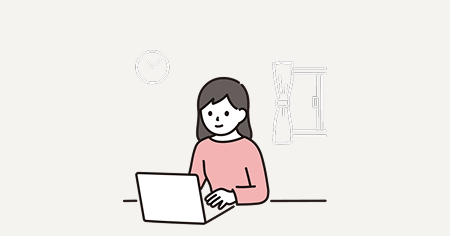こんにちは、はなです。
最近よく耳にする「AI副業はなくなる?」「Web制作はAIに奪われる?」という不安。
わたしもWeb制作を始めたばかりの頃、正直この言葉にドキッとして検索しまくりました。
スマホ片手に「AI 副業 終わった」って検索履歴を残しながら、
「え、私これから何を頑張ればいいの!?」って夜中にお布団の中でひとりパニック(笑)。
でも実際にAIを使いながら副業をしてみて分かったのは、
「AIに奪われる仕事」と「AIではできない仕事」がはっきり分かれる、ということ。
今日はその体験談と一緒に、AI時代の副業のリアルをシェアします。
Web制作はAIに奪われる?不安になる3つの理由
「AIに仕事を奪われる」って言葉、最近どこでも耳にしますよね。
でも実際に副業やWeb制作を始めようとすると、
「じゃあ自分も近いうちに必要なくなるのかな?」と不安になる人も多いはず。
実は、その不安の多くには“理由”があります。
まずは、なぜ「AIに奪われるかも…」と感じやすいのか、背景を整理してみましょう。
Web制作で「AIに仕事を奪われる」と不安になる背景
- ニュースやSNSで「AIが仕事を奪う」と言われすぎる
- ChatGPTやCopilotが“魔法のようにコードを書く”動画がバズってる
- 未経験者ほど「自分の仕事=単純作業」とイメージしやすい

にゃるほど〜。でも実務はAIに丸投げできるほどシンプルじゃないんだよ〜
ここで思い出してほしいのが、最近のソフトバンクの孫正義さんの言葉です。
みなさん知っていますか?
「人間の想像が限界に達したとき、AIがその先を見せてくれる」
これは2025年に開催された SoftBank World の講演で語られた言葉。
さらに孫さんは、世の中でよく聞く「AIの限界が見えた」という声に対して、
「それは“AIの限界”じゃなくて、“あなたの理解の限界”なんだ」
とも指摘していました。
わたしはこの言葉を聞いたとき、本当に衝撃を受けました。
この数年でAIの演算能力やモデルの精度は何十倍ものスピードで進化していて、孫さんは「これから先は、人間の想像を超える速さでAIは進化していく」とも語っています。
つまり──
AIの進化があまりにも速いからこそ、「自分の仕事がなくなるんじゃないか」という不安が生まれるんですよね。
でも同時に、AIに任せられる部分と、人間が考える部分はそもそも別物じゃないかと思います。
私たちが「もう終わりだ」と思う地点から、AIはむしろ新しい可能性を見せてくれる存在なんです。
とはいえ、そう言われても「じゃあ何が怖いの?」「なぜここまで不安になるの?」って思う人も多いはず。
そこで──
不安の正体=「AIに奪われる」のではなく「役割が変わる」だけ
1) 「限界」って、実は“見え方”の話
AIがミスる場面もあるけど、それを見て「ほら限界だ」と決めつけると、本当は使える場面まで見失う。
- 例:AIが書いたコードが一発で動かない→「ダメだ」じゃなくて、“たたき台としては速い”が正解。直して仕上げるのは人の役割。
2) 分業社会が進む=“ AIがやること / わたしがやること ”を分けるだけ
- AIが得意: 繰り返し作業、型が決まったコーディング、仕様の要約、素材探しの初動
- わたしの仕事: 目的の翻訳(要望→仕様)、デザインの方向付け、微調整と検証、「これで本当にユーザーは動く?」を判断
→ つまり、“置き換え”より“役割分担”の話。
3) 「速すぎて追いつけない」の正体は“情報量に圧倒される”こと
ニュースやSNSが毎日「新モデル」「新機能」。だから“全部やらなきゃ”病になる。
- 処方箋:月イチでツール見直し/週2回だけAI活用の練習時間を決める。ルール化すると不安は小さくなる。
4) 未知との共存は、“相棒化”でラクになる
AIを敵として見てるうちはずっと怖い。見習いアシスタントとして隣に座らせると、味方になる。
- 例:ワイヤーフレーム草案→AIに指示→出てきた案を“合格ライン”に合わせて直す(ここがスキル)
AIに奪われやすいWeb制作の仕事【実体験あり】
AIの進化が速すぎて「仕事を奪われるのでは?」という不安はリアルです。
ここでは Web制作の副業にしぼって、実際にAIを使いながら仕事をしているわたしの体感と、一般的に言われていることを合わせて整理してみます。
AIに奪われやすいWeb制作の仕事
AIは「パターンが決まっている」「正解がひとつに近い」作業がとても得意。
しかもその多くは、もうすでに実務レベルで使えるようになっています。
ここからは、わたしが実際に体感した“AIが得意で置き換えやすい作業”です。
① 単純なコーディング作業
ボタンの色変更とか、余白の調整とか、テンプレの複製って、ほぼ「型」が決まってますよね。
AIは過去のコードを山ほど学んでるので、こういう“お決まり作業”は一瞬で出してくれるんです。
実際に「LPのヒーローセクションをHTML+CSSで」って聞いたら、数秒でベースコードを返してくれます。
② 画像のサイズ調整やタグ置換
「この画像を小さくして」「WebPに変換して」「altをまとめてつけて」みたいな処理も、もうAIとツールの独壇場。
FigmaやCanvaには自動リサイズや最適化機能がついてるので、人がポチポチやるよりずっと速くて正確なんです。
③ サンプルコードの調べもの
ちょっと前までは「jQuery バリデーション」で検索して、Stack Overflowからコピペしてましたよね。
でも今はAIに聞けば一瞬で要点をまとめてコードを出してくれる。
GitHub CopilotやCursorなら、書いてる途中で「これ次に必要じゃない?」ってコードを提案してくれるほど。
④ テキストやコピーの“たたき台”
「お問い合わせフォームの文言」や「プライバシーポリシー」みたいな、形式がほぼ決まっているものはAIの得意分野。
ChatGPTにお願いすれば、一般的な内容をすぐに吐き出してくれます。
人がゼロから書くより、AIの原稿をベースに修正した方が圧倒的に早いんです。
⑤ 画像生成・デザイン小物
バナーの背景パターンやアイキャッチ画像、ちょっとしたアイコン。
これもAIが得意で、Canvaの「Magic Media」やAdobe Fireflyにキーワードを入れれば、すぐに“それっぽい”素材が完成。
「時間かけて探すより作らせた方が早い」ケースがどんどん増えてます。
⑥ コードのリファクタリング(整理整頓)
「このCSS冗長だから短くして」とお願いすると、AIはキレイに書き直してくれます。
正解がある程度決まってる作業はAIの得意分野なんですよね。
VS Code+Copilotを使えば、コメントを残すだけで改善提案を出してくれるので便利です。
AIではまだ難しい!人間にしかできない仕事
一方で、AIは「感覚や対話、責任が必要な部分」はまだ苦手。
ここからは、わたしが実際に感じた“人間にしかできない仕事”です。
① 独創性・刺さるデザイン
たとえば「女性向けでやさしい雰囲気に」とAIに指示すると、無難な配色やレイアウト、画像は返してくれます。
でも実際に見てみると「なんか心に残らない」「刺さらない」ことが多いんですよね。
AIが得意なのはあくまで“平均的なデザイン”。
独創性・センス・きめ細かい調整は、やっぱり人間の感覚が欠かせません。
AIの進化は確かにすごいけれど、まだまだ“人間らしい感性”が必要だと強く感じます。
② クライアントとのやり取り・責任ある提案
「もっと信頼感を出してほしい」みたいな曖昧な要望を具体化するには、人との対話がカギになります。
AIは会話はできても、人の曖昧な表現やニュアンスを正確に読み取るのはまだ苦手。
さらに、クライアントとの信頼関係を築くコミュニケーションはまだ人間にしかできません。
そして何より「これがベストです」と責任を持って提案する立場には、AIはなれないんです。
③ トラブル対応・全体最適の判断
AIが出したコードをそのままコピペして「動かない」なんてのはよくある話。
修正や検証はもちろん、サイト全体を見て「最短でどう直すか」を判断するのはまだ人間の強みです。
AIは目の前の1行を直すことはできても、全体を見渡して最適解を選んだり、複数の方向性から知恵を持ち寄ったりするのはまだ苦手。
AIは部分最適は得意でも、全体を見て複数の選択肢からベストを選ぶ知恵はまだまだ弱いです。
④ 文章の信頼性とニュアンス
AIは文章を量産できるけど、平気でうそを混ぜたり、誇張しすぎたりすることがあります。
「副業に興味がある看護師向けに安心感を出す文章を書いて」と頼んでも、事実より大げさだったり“響かない”ことが多い。
だからこそ、事実チェックや人間らしい共感表現は、人間の目と経験が必要なんです。
Web制作とAIの未来まとめ|奪われやすい仕事・残る仕事とは?
・AIに奪われやすい仕事 = 「ルール化・パターン化できる単純作業」
・AIに奪われにくい仕事 = 「人の感情に寄り添い、全体を見て問題を解決する仕事」
つまり──
AIを“敵”として恐れるよりも、 「任せられるところはAIに託して、人間にしかできない強みを磨く」 ことが生き残る鍵です。
AIが進化する時代だからこそ、
「AIに負ける人」ではなく 「AIを味方につける人」 が選ばれていきます。
こちらの記事もおすすめ
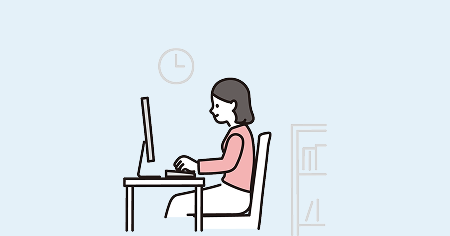
AI時代のWeb制作で生き残るために、これからどうすればいい?
AIに奪われやすい作業と、まだ残る人間の強みが分かったところで、大事なのは「じゃあ自分はどうすればいいのか」という視点です。
わたしが副業でWeb制作をしながら感じたのは、AIを怖がるより“共存戦略”を考えた方がラクってこと。
① AIを「使いこなす」スキルを身につける
AIは敵じゃなくて、効率化の相棒。
単純作業はAIに任せて、その分「提案」や「デザイン」など人間にしかできない部分に時間を割くことが大切です。
ここで重要になるのが “指示の書き方(プロンプトスキル)”。
AIは「大量の過去データをもとに“最も確からしい答え”を返す仕組み」なので、曖昧な指示=曖昧な答えになりがちなんです。
例えば:
- 「ボタンを作って」 → 形・色・配置がバラバラで再現性が低い
- 「青色の長方形で、角を丸めて、右端に配置するボタン」 → 一発でイメージに近いコードが返る
つまり、人に依頼するときと同じく「背景+条件+ゴール」をセットで伝えると精度が上がります。
Web制作でAIを使いこなす!精度を上げるプロンプト指示の基本(鉄則3+1)
1) 背景を伝える(Context)
何のため・誰向け・どこで使うかを最初に。
例:「看護師向けの副業LPで使う申し込みボタンを作ってほしい」
2) 条件を具体的に(Constraints)
色・サイズ・配置などは数値や値で指定。
例:「幅200px・高さ50px・角丸8px・青#2B6CB0・右端配置・ホバーで10%明度UP」
3) ゴールを明確に(Goal)
狙いたい印象やKPIを添える。
例:「やさしく信頼感のあるトーンで、CVR改善を狙いたい」
+1) 段階的に頼む(Steps)
一度で完璧を狙わず、たたき台→修正→最終化の順で小刻みに。
例:「まずHTML/CSSだけ→次に余白調整→最後にレスポンシブ対応」
NG例(AIが理解しにくい指示の出し方)
「ボタン作って」
情報が足りないから、AIはイメージ通りに出せずバラバラになりやすい。
OK例(AIが理解しやすい指示の出し方)
WebサイトのLPに配置するCTAボタンのHTML+CSSコードを作成してください。
用途:商品購入につなげるCTAとして使います。
条件:
- ボタン色はパステル調の青(#5ba9d9)
- 幅200px、高さ50px、角丸8px
- フォントはゴシック体、文字は「今すぐ申し込む」
- 文字色は白、ホバー時は少し濃い青に変化
- ボタンは親要素の右端に配置
デザインの方向性:女性向けで、やさしい雰囲気(柔らかさ・安心感)
② AIに真似できない「人間ならではの強み」を磨く
- 共感力(ターゲットやクライアントの気持ちを理解する)
- 提案力(曖昧な要望を具体化して、形にする)
- デザイン感性(“刺さる”配色や余白感はAIが苦手)
- トラブル解決力(エラーの原因を見抜いて直す力)
これらはAIがまだ不得意な部分。だからこそ、ここを磨けば「代替不可能な人材」になれます。
③ AIを学び続けるクセをつける → AIの進化に追いつく学び方【継続が武器になる】
AIの進化はとにかく速くて、「昨日までできなかったことが、来月には当たり前にできる」なんて普通にあります。
だからこそ大切なのは、新しいAIツールや機能を キャッチする力 と、それを実務で 使いこなすための学習力。
結局、ツールが進化しても「触って試す人」と「見てるだけの人」では差がどんどん広がっていきます。
学びを止めずにアップデートし続ける人こそ、どんな時代でも必要とされるんです。
どこでAI最新情報をキャッチする?おすすめ情報源
- 公式ブログ・ニュース
→ OpenAI、Google、Adobe などの公式発表は必ずチェック。新機能や事例はまずここから。 - SNS(X/YouTube)
→ クリエイターやエンジニアの「試してみた動画」「便利な使い方」でリアルな情報をキャッチ。 - コミュニティ(Discord・Slack)
→ 同じ分野の人と繋がり、実際の使い心地や事例をシェアできる。 - 学習プラットフォーム
→ UdemyやSkillshareで「AI×Web制作」「AI×デザイン」の最新講座を学べる。
どうやってAIを学ぶ?効果的な継続学習の方法
・習慣にする:週1で「AIニュースまとめ読み」、月1で「新ツールを触る」とルーティン化。
・小さく試す:新機能が出たら「自分のLPでボタンを作る」など1タスクで試す。
・人に説明する:学んだことをSNSやブログでアウトプットすると理解が深まる。
AIにコードを書かせてみた体験談|思わぬトラブルも…
わたしも実際にAIにHTMLやCSSを書かせてみたことがあります。
最初の感想は…
「おぉ!コード出てきた!」 → 「え?動かないじゃん…」
まるで夜勤中に点滴ルートが詰まって、
「え!?流れない!?患者さん寝てるのに!」と冷や汗かいたときの感覚でした(笑)
しかも別の日は、AIがとんでもなく長いコードを吐き出してきて、
「こんなに多い薬剤、本当に投与するの!?」って焦った夜勤のオーダーミスを思い出しました(笑)
そして正直に言うと…
時々「思い通りのコードを出してくれない!」ってイライラして、AIに八つ当たりしたこともあります。
「なんでこれでわからないの!?」「そっちじゃない!」って、まるで新人さんに「清拭セット持ってきて」って言ったのにタオルだけ持ってきたときの気分(笑)。
でも冷静になって見直すと、だいたい原因は わたしの指示がざっくりすぎたせい。
「ボタン作って」だけじゃ、AIはエスパーじゃないからピンと来ないんですよね。
「青色で、幅200pxで、角を丸めて、右端に配置して」ってちゃんと伝えたら、
「はい、かしこまりました!」みたいに一発で返してくれる。
つまり、AIに対しても「伝え方」で結果が全然変わる。
これは人と仕事するときと同じで、コミュ力(プロンプト力)がめっちゃ大事なんです。
ちなみに、わたしはAI(GPT)にこっそり名前をつけています。
呼ぶときは”名前”で声かけてるんですが、たまに思い通りに動かないと「”AIの名前”〜!何してんの!」って半ギレしてます(笑)。
でも機嫌を直して具体的に指示すると「了解だよ!」ってドヤ顔で返してくれる…そんな相棒です。
だから今はこう割り切っています。
- 単純作業やコードのたたき台はAIにお任せ
- エラーやズレた出力は“自分の指示のせいかも?”と一度立ち止まる
- 仕上げ・提案・調整は人間の仕事
こうすると、イライラよりも「相棒として頼もしいな」って気持ちの方が大きくなりました。
このスタイルにしてから、作業スピードは体感で2〜3倍。
夜勤で「バタバタしてご飯食べる暇もない」から → 「AIが土台を作ってくれるおかげで、わたしは仕上げに集中できる」へ。
同じ時間を使っても、ストレスが減って“楽しい副業ライフ”に変わりました。
Web制作とAI副業のまとめ|消える仕事・残る仕事
- 消える仕事(AIに置き換わりやすい)=ルール化・パターン化できる単純作業
- 残る仕事(人にしかできない)=共感力で人の感情に寄り添い、“刺さる”デザインを生むセンス、全体を見て最適解を選ぶ判断力、そして信頼を築くコミュニケーション力が求められる仕事
つまり──AIを敵として恐れるのではなく、
「任せられる作業はAIに委ねて、自分にしかできない強みを磨く」ことが大切です。
AI時代に選ばれるのは、AIに負ける人ではなく、AIを味方につける人。
あなたはどちらになりますか?
AI副業初心者が今日からできる小さな一歩【無理なく始める方法】
「でもまだ副業なんて無理そう…」と思った方へ。
いきなり案件を取る必要はありません。
スマホのメモに「やりたい副業」を3つ書く
気になるAIツールを1つだけ試す
このくらいの“小さな一歩”で大丈夫。
動き出すと、不思議と次の道が見えてきますよ。
\ 副業を始めるなら今がチャンス! /
AIはどんどん進化していきます。
だからこそ「まだ早いかな…」と思っている今こそ動き出す絶好のタイミングです。

読んでくださってありがとうございました。
今日もあなたの1日がいい日になりますように!